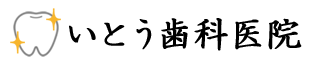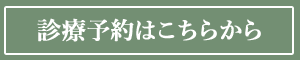杉並区西荻窪で入れ歯治療を数多く手がける
いとう歯科医院の伊藤高史です。
「作ってまだ3か月しか経ってないので修理できないと断られまして…」
おずおずといった感じではいっていらしたのは60代男性Dさん。
はじめに申し上げますと入れ歯を新しく作ってから、すぐでも保険治療で修理できます。
もちろん「全ての入れ歯に対して」作って直後に修理などという無茶な保険点数算定をしていたとしたら査定されるのは当たり前ですが、作ってすぐに何か壊れることはあります。
だから安心していただきたいと思います。
壊れたのは部分入れ歯を歯にひっかけて入れ歯を口の中に維持する金属バネ(クラスプ)。
左右の二つある中の、みぎ側クラスプの頬側(外側)だけが折れています。
長さとしては5ミリくらいのものです。
しかしその5ミリがないだけでもう入れ歯は使えなくなってしまいます。
舌を動かすだけで入れ歯はパカッと外れてしまいますし食事できなくなってしまったと言います。
保険治療の入れ歯には俗に言う「半年ルール」というものがあります。
それは新しい入れ歯を作ったら半年は作ってはいけない、というものです。
これは厳密に色々のケースによって解釈も色々あります。
また場合によっては半年以内でも作り替えが認められることがあります。
細かいケースについては気軽にお尋ねいただければ幸いです。
ともかく修理に関しては半年間も修理してはいけないルールはありません。
もっとも保険制度がどうのこうのと言うよりも考えなければいけないことがあります。
それは「なぜ3か月でクラスプが折れたか」です。
普通はそんなケースは少ないものです。
入れ歯を入れて噛んでもらってすぐに折れた原因が分かりました。
咬み合わせです。
一般的には上下で噛むと上の歯が下の歯を前側あるいは外側に覆うように並んでいます。
それがDさんの場合は一般的なケースと逆で下の歯が前に極端に出ています。
昔のプロレスラー、アントニオ猪木さんみたいな咬み合わせでした。
それでたまたま上の歯が下の入れ歯のクラスプに強くぶつかってクラスプを折ってしまったのでした。
治療方針としてはクラスプの修理です。
入れ歯を口の中に入れておいて型をとって、石こうを流して模型を作ります。
模型上でクラスプを作って入れ歯に埋め込んで修理完了。
金属ワイヤーから単純鈎を一つ屈曲するだけなので作業としては簡単です。
もっともクラスプ屈曲ができる歯医者は少ないので、冒頭のように断ってしまう歯医者はいます。
クラスプ屈曲さえできれば簡単な修理なので他の歯医者もやって欲しいものです。
部分入れ歯を作る費用は保険治療3割負担の方で総額約1~2万円
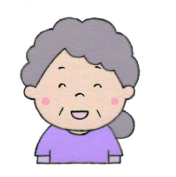
今回の修理で気をつけた点が2点あります。
まず一点目は型とりです。
クラスプが効いていないので口の中で入れ歯がフラフラ動いてしまいます。
歯医者が指で入れ歯を動かないように押さえながら型をとりました。
二点目はクラスプの位置です。
修理前と同じ場所にクラスプを設置したら、またクラスプが上の歯とぶつかって再び折れてしまいます。
上の歯とぶつからない位置に設置しました。
一般的にクラスプを修理するというと専門の歯科技工所に外注します。
模型を作って発注して作ってもらうと。
歯医者がクラスプを曲げて作れれば1時間でできるところを1週間はかかるので入れ歯修理としては現実的ではありません。
患者さんは1週間も入れ歯ナシというわけにはいかないはずです。
しかも歯科技工所は患者さんの口の中を知りません。
ともすると修理前と同じ場所に設置してしまいがちです。
それが一番簡単で、自然にそのような位置になってしまうからです。
患者さんの口の中がわかっている歯医者だからこそ、多少は屈曲が大変になるものの、口の中の状況に合ったクラスプを作ることが可能です。
そんなことで1時間で修理できた入れ歯は調整する必要なく口の中に収まりました。
「あっ、これならピッタリですね」
舌を動こしても入れ歯は浮きません。
Dさんは笑顔で帰られました。
今回行なったDさんの入れ歯のクラスプを修理する治療は、1回の通院で費用は保険治療3割負担で総額約4,000円でした(費用は治療部位や症状により変わります)。
入れ歯修理の難しさについて
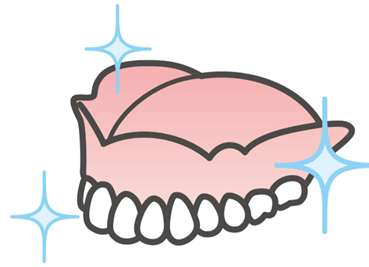
入れ歯は、失われた歯の機能を補い、生活の質を向上させる重要な医療機器です。
しかし毎日のように使われる中で、破損や劣化は避けられず、修理が必要となる場面は少なくありません。
この入れ歯の修理は、一見単純な作業に見えて、実は多岐にわたる専門知識と技術を要する非常に難しい作業です。
その難しさの要因は、主に以下の点にあります。
1. 材料の多様性と特性の理解
入れ歯は、レジン(歯科用プラスチック)、金属、セラミックなど、様々な素材を組み合わせて作られています。
それぞれの素材には、異なる物理的・化学的特性があり、破損の状況や部位によって、最適な修理方法、接着剤、補強材料が異なります。
たとえば保険治療で広く用いられるレジンの破損であればレジンによる修理ができるのですが、金属床の破損であれば溶接やろう付けといった特殊な技術が必要となります。
実際には難しく、当院もろう付けの設備はあるのですが、ほとんど使うことはありません。
また残っている歯が抜けたり折れたりした時に、入れ歯にプラスチックの人工歯を継ぎ足す増歯修理という技術があります。
その増歯修理が保険治療のプラスチック製入れ歯なら簡単にできます。
プラスチック同士なら問題なくくっつくからです。
しかし高額な自費治療の金属床入れ歯だとこの増歯修理が格段に難しくなります。
あるいは出来ないこともあります。
なぜなら金属とプラスチックはくっつかないからです。
金属に無理やり穴を開けてプラスチックを埋め込んだり溝を掘って物理的な嵌合力に期待したり工夫はします。
ただそもそも穴を開ける場所がないくらい細い金属板だったり溝を掘れるほどの厚さがなかったりします。
普通に保険治療のプラスチック入れ歯なら簡単の修理が自費治療の金属床になつているせいで苦労したり修理不可能になってしまったりします。
また近ごろ流行のシリコン入れ歯、ノンクラスプ入れ歯などというものがあります。
商品名としてはコンフォート、スマイルデンチャーなど。
このような入れ歯には最大にして致命的な欠点があります。
それは「修理できない」こと。
壊れたら、あきらめて新しく作るしかない。
痛くなったら、あきらめて新しく作るしかない。
ゆるくなったらあきらめて新しく作るしかない。
「最新鋭、最先端技術のシリコンによって夢のようによく合う!」
みたいに喧伝されるものですが実際には言うほどは合いません。
とはいえ無理にでも削って合わせたり、歯科専用の入れ歯安定材みたいな材料ティッシュコンディショナーを無理やり貼り付けたりすることはあります。
ただあまり改善はできないのが実情です。
これらの材料特性を熟知し、適切な材料を選択する知識が不可欠です。
保険治療で歯が抜けた部分を入れ歯に継ぎ足す増歯修理

2. 精密な適合性の再現
入れ歯は、患者さんの口腔内の形状に正確にフィットすることで、安定した噛み合わせと快適な装着感を提供します。
破損した入れ歯を修理する際、元の適合性を完全に再現することは非常に困難です。
わずかな歪みやずれでも、噛み合わせの不調や粘膜への圧迫、さらには発音の障害を引き起こす可能性があります。
だから先に紹介したように、口の中で動かないように型をとる工夫が必要です。
ただ押さえる場所がないとか難しいケースもあります。
とくに、クラスプ(維持装置)の破損や、床(しょう:歯肉に接する部分)の破折の場合、口腔内の複雑な湾曲や歯列との関係性を考慮した上で、ミクロン単位の精度で修理を行う必要があります。
クラスプ修理は、写真で拡大してもスキマが見えないくらいの精度が必要です。
たとえば歯科技工所でクラスプを作ると、どうしてもそのスキマがないほどの精度ができない場合があります。
だから当院では入れ歯を作る際は歯医者が自分でクラスプを屈曲して発注のときにそのクラスプを技工所に渡して使ってもらうこともあります。
3. 口腔内環境の複雑性
入れ歯は、常に口腔内の湿潤で温度変化のある環境に晒されています。
唾液、咀嚼圧、清掃時の力など、様々な要因が入れ歯に影響を与えます。
修理後にこれらの口腔内環境に耐えうる強度と耐久性を持たせるためには、単に破損部位を接着するだけでなく、応力集中を避けるような設計変更や、適切な補強を施す必要があります。
これも先にご紹介した、クラスプの形の作り方を工夫して上の歯とぶつからないようにした、という話です。