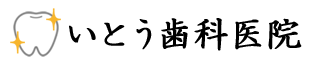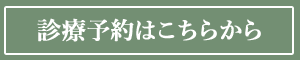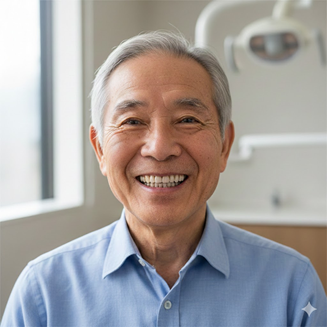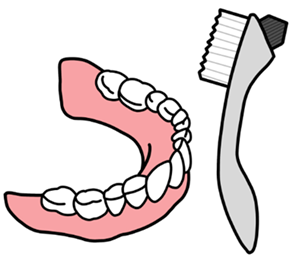西荻窪にあるいとう歯科医院の伊藤高史です。本日のテーマは「コーラを飲むと歯が溶けるは本当?」といった話です。
よく「コーラばっか飲んでると歯が溶けるよ」とは昔から言われた話。
「コーラを飲むと歯が溶ける」という話は、半分本当で半分誤解です。正確には、コーラに含まれる酸によって歯の表面のエナメル質が溶けやすくなる、というのが事実です。
コーラにはリン酸や炭酸が含まれており、pHはおよそ2~3程度と強い酸性です。歯のエナメル質はpH5.5以下で脱灰(だっかい)といって、ミネラルが溶け出す現象が起こります。そのため、コーラを長時間・頻回に飲む習慣があると、歯の表面が少しずつ溶け、酸蝕症(さんしょくしょう)と呼ばれる状態になることがあります。
ただし、1回飲んだだけですぐに歯がボロボロに溶けるわけではありません。口の中には唾液があり、酸を中和し、再石灰化を助ける働きがあります。問題になるのは、ダラダラと長時間飲むことや、就寝前に飲んでそのまま寝てしまうことです。
対策としては、コーラを飲んだ後に水で口をゆすぐこと、時間を決めて飲むこと、すぐに強く歯みがきをしない(酸で軟らかくなった直後は30分ほど待つ)ことが大切です。
「コーラで歯が溶ける」は極端な表現ですが、飲み方次第では歯にダメージを与えるのは事実。頻度と習慣が鍵になりますので飲み過ぎには注意しましょう。