杉並区、西荻窪で、保険の入れ歯治療を数多く手がける歯医者、いとう歯科医院の伊藤高史です。
オルタナティブブログに記事を載せました。
部分入れ歯の金属バネ(クラスプ)が折れたので、歯科医師が新しく作製した症例↓
https://blogs.itmedia.co.jp/ito_takafumi/2025/06/content_8.html
ホームページ掲載 すみ
杉並区、西荻窪で、保険の入れ歯治療を数多く手がける歯医者、いとう歯科医院の伊藤高史です。
オルタナティブブログに記事を載せました。
部分入れ歯の金属バネ(クラスプ)が折れたので、歯科医師が新しく作製した症例↓
https://blogs.itmedia.co.jp/ito_takafumi/2025/06/content_8.html
ホームページ掲載 すみ
杉並区西荻窪で入れ歯治療を数多く手がける
いとう歯科医院の伊藤高史です。
「歯がグラグラで入れ歯がつかえなくなったんです」
3年ぶりに来院されたのは60代女性のGさん。
みぎ上の前から3番目の歯が抜けそうなくらい大きく揺れています。
いっそのこと自然に抜けてくれたら患者さんも歯医者もラクです。
麻酔の注射をしなくて済みますから。
しかしそう簡単には自然に歯が抜けることはありません。
そこで今回は、みぎ上3番を歯を抜くことにしました。
Gさんは部分入れ歯を使っています。
これまでずっと、グラグラしている歯を抜いたら、その抜いた部分はプラスチック製人工歯を部分入れ歯に継ぎ足す増歯修理を繰り返してきました。
最後に治療してから3年間ずっと調子よく使っていたそうです。
今回も修理の内容としては同じです。
みぎ上3番を抜歯していた部分はプラスチック製人工歯を部分入れ歯に継ぎ足す増歯修理。
これまでずっと、みぎ上3番の歯に金属バネ(クラスプ)を引っかけて入れ歯を口の中に維持してきました。
今回抜歯するとクラスプが効かなくなってしまいます。
他に1つクラスプが奥にあります。
しかしクラスプが2→1つになると入れ歯は簡単に外れてしまって使えなくなります。
そこで手前のみぎ上2番は健全な歯でしたので、そこに新たにクラスプを作る修理を行なうことにしました。
口の中の型をとって石こう模型を作ります。
模型に入れ歯を合わせておいて模型上で歯医者が自分でワイヤーを屈曲してクラスプを作る。
歯科用プラスチックでクラスプを入れ歯に埋め込んで出来上がり。

工程としては単純なものの、ひとつ問題がありました。
それは入れ歯の適合が悪いこと。
口の中でもあまり合っていなかったとはいえ模型と入れ歯も合いません。
やはり3年間ずっと調子よかったとはいえ放置していたのでアゴの形が変わってしまっています。
そのようなことで定期的に歯医者に通うことの重要性はご説明させていただきました。
それはともかく、そんな中でも修理は必要です。
なんとか模型と入れ歯が合う場所を見つけました。
また前から2番目の歯は一般的に細長いです。
だから型に石こうを注いで模型を作る時もひと工夫が必要です。
それは細い金属線を埋めこむこと。
こうすることで折れにくくなります。
しかし努力の甲斐なく石こう模型はボッキリ折れてしまいました。
とはいえ石こう模型が折れてから実は金属線が威力を発揮します。
石こうだけだと砕けてしまったら元のように再現できなくなってしまいます。
それが金属線のおかげで折れ口がピッタリと合うのです。
ピッタリと合わせておいて歯科技工用の瞬間接着剤を流して模型の修理は完了。
さっそく修理し始めます。
模型上でクラスプを屈曲して合わせます。
このように合っているか分からない入れ歯を修理する際は、クラスプはピッタリ合わせすぎずルーズに合わせます。
歯とクラスプにスキマが見えるくらいです。
なぜなら入れ歯が口の中で合わない、模型と口の中とで誤差が生じる可能性があるからです。
模型上でピッタリすぎると、模型と口の中とで誤差があった場合には、口の中で合わない、装着できなくなります。
しかしルーズにしておけばスキマはあるものの入れ歯が口の中に収まります。
歯とクラスプのスキマはワイヤーを少しずつ屈曲して合わせることが可能です。
このような修理はワイヤー屈曲だからこそできる芸当です。
近ごろは歯科技工士でさえもこのワイヤー屈曲ができなくなっています。
昔は入れ歯を作る技工士ならば誰でも当たり前のように屈曲できました。
私もある勤務先の大きな歯医者で院内に技工所を備えていました。
そこの技工士さんからクラスプの屈曲を習いました。
別に卓越した技術の持ち主だったわけではなく保険治療の技工物を作製する並の腕前の技工士さんです。
しかし最近ある大学病院の歯科技工所はもうワイヤー屈曲できる技工士がいないという話を聞いたことがあります。
それではどうやってクラスプを作るか?

模型上でワックスでクラスプの形を作ります。
それを耐熱性の石こう、埋没材に埋めて熱を加えます。
そうするとワックスが溶けて空洞ができます。
その空洞に熱して溶かした金属を流しこむ「鋳造(ちゅうぞう)」という方法でクラスプを作ります。
鋳造クラスプは強度があって歯に引っかかる力が強い。
だから入れ歯を口の中に維持できます。
ただ欠点もあります。
維持力が強すぎて逆に歯を抜く力がかかってしまうことです。
後は入れ歯を着脱する際にクラスプに力が加わります。
そのせいでワイヤーと比べるとしなやかさ、柔軟性(展延性)に劣る鋳造クラスプは金属疲労を起こして、ある日突然ボッキリ折れます。
また今回のような、そもそも適合が不確実な症例では絶対に合わせることはできません。
後は工程が多いです。
・石こう模型を作る
・ワックスで形を作る
・埋没材に埋めて硬化するのを待つ
・熱してワックスが溶けるのを待つ
・金属を溶かして流しこむ
・金属が固まるのを待つ
・埋没材を壊してクラスプを掘り出す
・研磨する
・完成したクラスプを入れ歯に埋めこむ修理をする
とてもじゃありませんが鋳造クラスプを作っていたら1時間で入れ歯修理するのは不可能です。
その点、ワイヤークラスプならば
・石こう模型を作る
・ワイヤーを10分くらいで屈曲
・完成したクラスプを入れ歯に埋めこむ
これで出来上がり。
クラスプを曲げる技術さえあれば、入れ歯修理はもう鋳造クラスプでは勝負にならないと思います。
修理した入れ歯は意外にも口の中にピッタリと合いました。
入れ歯と模型は、合わないなりに合わせる方法はあります。
入れ歯を上アゴの口蓋部分にピッタリと合わせて修理しました。
口蓋部分は年月が経っても比較的変形が少ないといわれています。
今回はそのような知識が功を奏しました。
「あっ、これなら外れないですねー」
Gさんは笑顔で答えてくださいました。

もちろん長年診ていなくて入れ歯は不適合が大きいし歯、歯グキの状態も悪いです。
とはいえ使える入れ歯さえあれば後はゆっくり治療を行なって改善していきます。
・他にグラグラしている歯があるので、そんな歯を抜く。
・クラスプが引っかかっている歯はムシ歯があるので治療する。
・歯グキの状態が悪く歯と歯グキの境目の深さが5ミリ程度もあるので歯石除去やブラッシング指導を通じて改善していく。
もし入れ歯修理ができなかったら、どのような治療方針になりますでしょうか?
おそらく新しく入れ歯を作るしかないでしょう。
しかしその治療方針では上手くいかない可能性が大きいです。
だから入れ歯を修理しました。
なぜなら入れ歯を新しく作るには、他の歯、歯グキの状況が悪いからです。
そちらの治療から始めていたら、それだけで1か月はかかります。
それから入れ歯を作り始めるわけですが、やはりプラス1か月かかります。
2か月以上も入れ歯を使えないので歯がないまま過ごしていただかなければならないことになります。
治療に進展がないまま2か月も過ごす。
私が患者の立場だったとしても、そんな根気は保てません。
もう歯がないままでいいや…
ことになります。
そしてますます入れ歯が入らなくなってしまう。
そんな不幸な患者さんを増やしてしまいます。
それに引き換え完璧とは言い難いものの、とにかく入れ歯修理さえできれば、初回でもう入れ歯があって歯並びを回復できています。
後のことは患者さんは、ゆっくり構えていれば大丈夫。
患者さんも歯医者も落ち着いて治療していきましょう。
Gさんは仕事をしている方です。
入れ歯修理さえできれば時間の融通が効きます。
仕事の都合に応じて週1回~2週に1回くらいのゆったりペースで通っていただいて順調に経過しています。
杉並区、西荻窪で入れ歯修理を数多く手がける
いとう歯科医院の伊藤高史です。
「あしびきの 山鳥の尾の しだり尾の ながながし夜を ひとりかも寝む」
万葉集に数多くの詩を残し百人一首にも載っている柿本人麻呂。
持統天皇などと交流があり下級役人として旅し石見にて病で亡くなった。
この定説を舌鋒鋭く批判し真実を追究する「水底の歌」梅原猛著、新潮文庫。
一般書でありながら学会論文をひもとくみたいな論の積み重ねに、私は引き込まれるように読み進めていました。
・定説が出来上がった過程には真偽と関係なく研究者の思い込みが入っている。
・その思い込みを論破されないように「この歌は後世の作り話」など苦しい言い訳をする。
・反対意見は権威で潰すなど。
どこの世界でもありがちなウラの姿もよくわかります。
ふと思い浮かんだのは、自分の歯科治療です。
思い込みで突っ走っていないか。
思い通りにいかない時に苦しい言い訳をしていないか。
患者さんの話を権威で潰していないか。
歯科治療とは常に客観的な検証が必要です。
柿本人麻呂の人生がどのようなものだったか。
研究者や時代によって「定説」とされるものが何回も変わってきました。
有名な百人一首の歌も、実は柿本人麻呂の作ではないと今回調べて初めて知りました。
それと同様に歯科治療の「定説」たとえば歯磨きのやり方や咬み合わせの理論、いわゆる顎関節症の扱い、抗菌薬など数十年の間にガラリと変わったものがあります。
とくに歯が一本もない患者さんの下アゴの位置を決める基準として「中心位」という言葉があります。
私たちが学生のころの中心位の定義とは
下顎最後退位(下顎頭が下顎窩内において最後退位にある状態)と習いました。
下アゴを後方にさげるためのセントリックなんとかというチリトリみたいな器具で患者さんの下アゴをグイグイと押し込んだものです。
しかしそれを指標としてかぶせものを作ると、顎の関節に症状を起こすことが明らかになりました。
そこで現在は
「下顎頭が関節円盤を介して、関節腔の前上方に位置している状態」
と定義が変わりました。
正直なところ、分かったような分からないような定義です。
とはいうものの何かの基準は必要です。
結局は大ざっぱに
「中心位とは、健康な顎関節における最も安定している位置」
というところに落ち着いているようです。
参考文献:Search Labs | AI による概要
定義はともかく、患者さんの安定して噛めるアゴの位置を決めるためのノウハウはあります。
自分もこれからも勉強し続けて変化に柔軟に対応していくつもりです。

もっとも歴史の世界にある真実は一つだけです。
だから今は多くの意見があっても、研究が進むにつれて結論は段々と一つに集約されていくことでしょう。
それに比べて医療の世界の真実は一つではありません。
同じ患者さんを治療するのも、私が行うのと他の歯科医師が行うのとでは結果が変わってきます。
別に保険治療と自費治療のどちらが良いとか悪いとかいう話ではありません。
また同じ患者さんを私が治療するにしても、今すぐ治療するのと1年後に治療するのとでは結果が変わってきます。
一つの真実などというものはなく限りなく拡散する世界。
その中で入れ歯で治す、インプラントで治す、歯周病治療が得意など、自分なりの方向性を決めて進むことが求められます。
とはいえ歯科医師の目指す真実はただ一つ「患者さんのために」です。

歴史研究と歯科治療。
違う世界ですが、一つの真実を求めるために数多くの書物を研究し論を導く。
パソコンなどで調べると、この梅原説にも不審な点があると指摘されています。
とはいえその探究心には大いに触発されました。
ちなみに平安時代に編纂された古今和歌集において柿本人麻呂は「歌聖」と呼ばれました。
これは単純に「柿本人麻呂すご~い」というだけの話ではありません。
他に「聖」とされた歴史上の人物として挙げられるのは聖徳太子、菅原道真、千利休など。
いずれも政治的に恵まれず追放や孤独、非業の最期を遂げています。
だからこそ「聖人」として祭られる。
著者の梅原氏も、この辺りの事情から柿本人麻呂の人生について定説をくつがえし大胆な提起をしています。
実は持統天皇など最高権力に近いところにいながら、時の実力者だった藤原不比等と何らかの対立があり…
これ以上の内容については書を読むことをお勧めします。
読みながら「ボクも入れ歯治療の聖人なんて呼ばれたいな~」とボケーッと考えはしました。
しかし歴史上の偉人、聖人などには全く及ばない上に、普通に家族と幸せに暮らしたい小人です。
そんな自分には「入れ歯治療がんばってます」くらいの称号で十分であります。

まず歯ブラシは柔らかいもの~普通のもの、を選びます。
少なくとも3か月ごとに新しいものに交換することが重要です。
あまり長い期間、同じ歯ブラシを使用すると磨く効率が下がる可能性があります。
歯磨き粉はフッ素入りのものを使用すると、虫歯予防に効果的です。
参考文献:Search Labs | AI による概要
歯磨き粉のフッ素濃度は、国が定めた公的な基準で1,500ppm(ピーピーエムエフ)までです。
一般的には1,450ppmまでに抑えられています。
フッ素濃度は、年齢やむし歯のリスクによって異なります。
歯が生えてから2歳:1,000ppm(米粒程度)
3~5歳:1,000ppm(グリーンピース程度)
6歳以上:1,450~1,500ppm(歯ブラシ全体程度)
う蝕のリスクのある16歳以上:5,000ppm(1日2~3回)
フッ素濃度が高い歯磨き粉は6歳未満の子供には使用を控える必要があります。
年齢に応じた物を使ってください。
また誤飲を防ぐために子どもの手が届かない場所に保管します。
歯磨き粉のフッ素濃度はパッケージの表面や裏面に「〇〇〇ppmF」や「〇〇〇ppm」という表記があります。
昔は高濃度フッ素という発想がありませんでした。
上記の歯磨き粉のフッ素濃度の推奨基準は2023年1月に変更されたものです。
かなり最近です。
この変更は、日本小児歯科学会、日本口腔衛生学会、日本歯科保存学会、日本老年歯科医学会の4学会合同の提言によるものです。
フッ素濃度の推奨基準が変更された理由としては、次のようなことが挙げられます。
・国際歯科連盟(FDI)や世界保健機構(WHO)など国際的な機関では年齢にかかわらずフッ素濃度1,000ppm以上の歯磨き剤が推奨されていること。
・フッ化物応用の研究が進んだことで、より精度の高い基準を設けることが可能になったこと。
フッ素濃度は「ppm」という単位で表され、1ppmは100万分の1%を意味します。

歯磨きは朝と夜の2回、1回あたり2分間以上、行なうのが理想的です。
ブラッシングの順序:
歯の外側から始め、次に内側、最後にかみ合わせの面を磨きます。
とくに歯の裏側や歯と歯の間はプラークが溜まりやすいので丁寧にブラッシングしましょう。
ブラッシング方法:
バス法:
歯と歯茎の境目を45度の角度でブラシを当て、細かく振動させる方法です。これにより、歯と歯茎の間の汚れをよく落とすことができます。
私が歯科学生の頃は歯磨き法といえばこのバス法一辺倒でした。
ただ歯ブラシの毛先が動かないように小さく動かすとか難しいテクニックが必要で、全部の歯を磨くのに30分とか必要になるので大変かと個人的には思います。
とはいえ歯科医院で歯科衛生士からおそわるのは、ほとんどバス法です。
科学的根拠はある方法なので指導されたらやってみてください。
ローリング法:
歯の表面にブラシを垂直に当て、歯の先端から根元に向かってブラシを転がすように動かします。
これは特に歯茎マッサージにも効果的です。
ブラッシングの動き:
小刻みに動かすのがポイントで、大きな動きで磨くと歯茎を傷つける可能性があります。
とはいえバス法よりは大ざっぱに動かして大丈夫なので小児の歯磨き法で用いられます。
力を入れすぎず軽いタッチで円を描くように磨きましょう。
杉並区西荻窪で入れ歯治療を数多く手がける
いとう歯科医院の伊藤高史です。
「うまくいっている歯科治療はどれも似たものだが、うまくいっていない歯科治療はいずれもそれぞれにうまくいっていない理由がある」
自分で読んでもうっとりするようなカッコいい文章ですが、もちろん語彙力と読解力に難がある私のオリジナル文章ではありません。
文豪トルストイの小説「アンナ・カレーニナ」の有名な書き出しの部分を少し変えたものです。
「幸福な家庭はどれも似たものだが、不幸な家庭はいずれもそれぞれに不幸なものである」(中村融訳、岩波文庫)
結婚生活が幸福であるためには、異性として互いに惹かれていること、運命を味方につけること、その場の勢い、金銭感覚、食事の好み、子どもの教育方針、収入、親族との関係など。
多くの事柄と条件において鍋とフタのようにピタリと一致していることが必要。
逆にどれかひとつでも欠けると、とたんに瓦解する。結婚生活とは綱渡りのようなものです。
うーん確かに。
もっとも私自身は今のところ妻が人格者なおかげで幸福に過ごしています。
それはさておいて、このことが結婚生活以外にも当てはまる話を「銃・病原菌・鉄」上(ジャレド・ダイアモンド著、倉骨彰訳、草思社文庫)で読みました。
なぜヨーロッパ人がアメリカ大陸、アフリカ大陸、オセアニア大陸の先住民を駆逐し富を築くことができたのか、逆になぜアフリカ人がヨーロッパを占領することにならなかったのか、鋭く精緻な分析で読み解くスリリングな本です。
たくさん理由がある中で
「ヨーロッパを含むユーラシア大陸では多数の大型動物を家畜化するのに成功したから」
と述べる部分でページをめくる手が止まりました。
家畜というとたくさんいそうなものですが実は世界中に14種類しかいません。
牛、羊、ヤギ、豚、馬、ラクダ、ラマ、アルパカ、ロバ、トナカイ、水牛、ヤク、バリ牛(東南アジア)、ガヤル(インド、ビルマの牛)。
こういった動物は多くの条件、事柄がピタリとうまくいったおかげで家畜化に成功しました。
家畜ができたことで食料生産が増えて人も増えて豊かになって、騎馬兵のような強力な武器もできて新しくアメリカ大陸やアフリカ大陸に進出できました。
家畜化できそうな哺乳類は、とくにアフリカなどは昔のテレビ番組「野生の王国」のように大型動物の宝庫に見えます。
しかしアフリカ原産の大型動物で家畜化できたのはゼロです。
カバ、サイ、ライオン、シマウマなど家畜になっていません。
書によると家畜化の候補となった大型動物は72種類いたそうです。
ユーラシア大陸ではそのうちの13種類を家畜化できました。
これは多いように見えるものの家畜化率としては18%に過ぎません。
「家畜化できている動物はどれも似たものだが、家畜化できていない動物はいずれもそれぞれに家畜化できないものである」
銃・病原菌・鉄の書で、アンナ・カレーニナの文章を借りてそう述べられていました。
私が歯科治療について書いたのはマネのマネです。
それではなぜアフリカ動物は家畜化できなかったのか。
それぞれに理由が挙げられていました。
・エサがあまりに大量に必要
・成長が遅すぎる
・繁殖させにくい
・気性が荒すぎる
・逆に神経質すぎる
・集団生活できないなど
つまり家畜化がうまくいった理由とは、その動物を人間に都合の良い、数少ない型にうまく当てはめることができたからです。
家畜化がうまくいかなかった理由はアフリカの野生動物を思い浮かべれば納得いきます。
庭でライオンを飼っている人はいません。
競馬でシマウマは走っていません。
カバの乳を飲んだことはありません。
このような話を読んで私がふと思い浮かべたのが、高額で大がかりな歯科の自費治療でした。
保険治療の入れ歯なら総額1万円ほど。
装置も小さく簡単で、歯科医師が自分で作ることも可能なくらいです。
それが自費治療になると、インプラントをはじめ、金属床入れ歯、インプラント4本で全顎を覆うオールオンフォー、セラミック冠、ジルコニア、特殊なアタッチメント、シリコン入れ歯など。
装着するまで年単位で時間がかかり金額が百万円を越えることも珍しくありません。
大がかりで高額な治療の候補はもっとたくさんあります。
私は自費治療をやらないのでこの程度しか書けません。
自費治療を数多く手がける歯科医師なら治療法を72種類くらいすぐに思いつくのではないでしょうか。
しかし歯科の大がかりな自費治療はアフリカの大型哺乳類と同様に、やはり一筋縄ではいかないものです。
トラブル、失敗を数多く見てきました。
なぜこの症例は失敗しているのか。
理由ならいくらでも挙げられます。
全身状態の不良
喫煙
咬み合わせの不正
口腔清掃の不良
顎の骨の弱さ
歯ぎしり食いしばり
ストレス
歯科医の説明不足
治療方針の間違い
歯科医の技術不足
治療部位への力の過重負担
口の乾燥が著しい
全身的疾患との兼ね合い
診断が間違っていた
など。
保険治療のような小さな術式なら必要な条件も少なく、上記のような多少の不具合にも迅速に柔軟に対応できます。
やはり大がかりな治療を行うなら、あらゆる条件、事柄がピタリとうまくいく必要があります。
しかし何かひとつが欠けたらガタガタッと崩壊してしまう。
そんな例は枚挙にいとまがありません。
とくに大型哺乳類の代表格ゾウを飼い慣らして戦争の戦力にしようとして、歯科の自費治療のように失敗した話を読みました。
「アド・アストラ」(カガノミハチ著、集英社)
紀元前の地中海を舞台としたイタリアのローマ帝国とアフリカの古代カルタゴ国(現在のチュニジアあたり)の戦争を描いた漫画です。
カルタゴは主戦力のゾウを率いてローマに攻め入ります。
有名な「ハンニバル将軍のアルプス越え」です。
はじめは巨体のゾウに押されていたローマ軍でしたが、脇や耳など柔らかい弱点を槍で突くことでゾウをパニック状態にして攻略。
最後はカルタゴを占領しました。
このようにゾウには致命的な欠点、弱点があるためローマ帝国はゾウを戦力にすることはありませんでした。
逆にローマの戦力になったのは、スピードある馬を自由自在に駆り小型の投げ槍で相手戦力を削るヌミディア騎兵と、盾で防御しつつ短い剣グラディウスで接近戦を強化した軽装歩兵です。
小型で小回りの利く新しい武器と組織力を用いて、まさに小よく大を制す発想でカルタゴのゾウ軍団を倒したローマ。
私は読みながら喝采を送っていました。
家畜化にしても小型の動物なら簡単です。
イヌ、ネコ、インコ、カメ、金魚などエサも少なくすみ、場所もとらない、性格も温厚です。
もちろんペットとして世界中に広まっています。
わが家で20年以上飼っているクサガメのタロウ君は最近お手をするようになりました。
実はメスだったらしいと後からわかって焦っているところですが、小さい動物なら私ひとりの力でも飼える実例です。
歯科の保険治療における欠点としてよく言われるのが、材料や治療法に選択の余地が少ないことです。
しかしそれは必ずしも悪いことではありません。
なぜなら保険治療に採用された治療法は、厚生労働省や大学病院などでケタ違いの数、お金、頭脳、力がかけられて選ばれているからです。
個人が思いつきで編み出した施術など相手にされません。
個人で同じくらい信頼に値するデータを作ることなど不可能だからです。
だから小型で簡単で小回りが利き、組織力に担保された保険治療なら安心して進められるのです。
それにひきかえ歯科の自費治療には数多くの候補があります。
そのうちどのくらいの数が生き残るのでしょうか。
・科学的根拠に乏しいもの
・院長ひとりのカリスマ性だけで突っ走っているもの
・トラブルになったら誰も解決できないもの
・後から修理調整が一切できないもの
・学会で正式に否定されたもの
など。
歴史の重みに耐えられるようには思えないのです。
古代カルタゴではゾウを家畜化、戦力化しようとして失敗しました。
歯科の自費治療もそのようにひとつ消え、ふたつ消え、結局は成功例18%くらいなのかも知れません。
「アド・アストラ」の作者はあとがきに書いています。
「この物語を描いている最中、カルタゴやローマや周辺国を現代の日本や国際情勢に当てはめて考えることが多々ありました。二千年以上経た今も人間は同じようなことを繰り返しているものなんですね」
歯科の世界も同じようなことを繰り返しているものなんですね。
これからも歯科治療と同時に歴史もさらに勉強して、患者さんにとって最良の選択をしていきます。
【関連記事】→入れ歯の扱い方
杉並区、西荻窪で入れ歯修理を数多く手がける
いとう歯科医院の伊藤高史です。
時は紀元前の中国、国が分裂し群雄割拠していました。
その国の一つ秦では秦国内を二分する内乱が繰り広げられます。
圧倒的多数の反乱軍。
攻められる王軍はしかし反乱軍大将、戎てき公(じゅうてきこう)の軍勢を分離させ、崖に追い込むことに成功していました。
王軍の軍師「河了貂(かりょうてん)」は戎てき公を討ち取るために、崖と三方の軍勢で壁を作り敵軍を囲い込む戦術「包雷」を決めます。
本来は広い場所で圧倒的多数で敵を囲む包雷ですが、数で劣る王軍の軍勢は壁を一列に作るのが精一杯。
「とにかく壁を破られないように持ちこたえて」
と兵を鼓舞する河了貂。
薄皮一枚のような壁を崩そうと数で押し込む敵勢を前に、包雷を維持できる時間はわずか。
チャンスは一回のみの超短期決戦を挑みます。
そんな包雷の中を、王軍手練れの将が突撃、一撃必殺で戎てき公の首を獲る。
…秦の始皇帝を描いた漫画「キングダム」を読んで頭の芯が痺れるのを感じました。
私も診療で河了貂のような状況に置かれることがあるのを思い出したからです。

保険治療が中心の当院は、基本的には亀のようにじっくりと時間をかけて丁寧に取り組むのを旨としていますが、時にはこの河了貂の作った包雷のような策を挑むことがあります。
たとえばグラグラ揺れている歯が一本あります。
他に歯はなく、口を閉じてもらうとグラグラの一本だけに頼って咬み合わせの位置を保っている症例。
まさに河了貂が作った包雷のように薄皮一枚で保っている咬み合わせです。
明日には歯が抜けてしまうかも知れない。
するとどこで咬めばいいのか患者さん自身も分からない咬合崩壊を引き起こします。
治療が格段に難しくなるのです。
そんなときに超短期決戦を仕掛けます。
迷ってはいけない。
歯が抜けないように、硬化しても柔らかさが残るアルヂックスという今ではあまり使われない旧式の型採りの材料を用いて、口の型を採り模型を作ります。
一般的には専門の歯科技工所に発注して数回かけて入れ歯を作るところを私が自分で作製。
すると次回には入れ歯が口の中に入ります。
薄皮一枚のところで咬み合わせを保っているグラグラの歯に歯科医師作製の入れ歯を入れて、入れ歯で咬み合わせを作ります。
ここまで態勢を整えれば、グラグラの歯はいつ抜けても咬み合わせは無事に保たれます。
圧倒的不利な状況を、自作の入れ歯を武器に短期決戦、一撃必殺で逆転勝利へ導く。
患者さんが笑顔で帰られるのを確認してから一人で拳を振り上げ
「ヨッシャー!」
見事勝利した河了貂たちのように勝ち鬨(かちどき)を挙げます。
これだから歯科医師は楽しい。
心からそう思える瞬間なのです。
参考文献:キングダム40巻 原泰久著 集英社

入れ歯でカチッと噛んだ時の位置、咬み合わせを決めるプロセスは、歯医者の専門知識と患者さんの口腔環境を考えて行ないます。
残っている歯、生えている歯が今回の症例のように一本でもあれば
「はい、カチッと噛んでください」
と歯科医師が言って患者さんが上下の歯でカチッと噛めばそれだけで多くの場合、解決します。
いつも快適に安定して噛める場所が1箇所に定まれば良いわけです。
しかし歯が一本もなく入れ歯もなかったら、どうでしょう?
噛む場所が分かりません。
すると入れ歯の咬み合わせを決めることが格段に難しくなります。
そこで咬み合わせを決める様々な方法があります。
とはいえ、その前に患者さんの口の中やや顎の形を知ることが必要です。
歯がある場合には赤い色のついた薄い紙、咬合紙を噛んでもらうことで咬み合わせを把握できます。
しかし歯がない場合は当院では主に二つの方法で咬み合わせを決定します。
1.患者さんが現在使っている入れ歯を直接使う
石こう模型に入れ歯を直接合わせて咬み合わせとなる対合する模型と組み合わせて、咬合器という機械に取り付けます。
患者さんの普段使っている入れ歯を用いるので信用できます。
ただ模型と入れ歯がピッタリと合う時ばかりではないので後から修正が必要になることもあります。
2.仮のワックス床を使う
たとえば
「歯がない、入れ歯もない」
という方は、どうすれば良いでしょうか?
ワックスでできた仮の入れ歯を模型に合わせて作ります。
そのワックス床を口の中に入れて噛んでもらって咬み合わせを記録します。
ワックスを熱で柔らかくして口を閉じてもらうやり方です。
熱し方や口を正しい位置に誘導するやり方など様々なメソッドがあり、私もいくつか知識にあって役立てています。
とはいえ中々難しいのが現状です。
その他のやり方として、ゴシックアーチという器具を使う方法もあります。
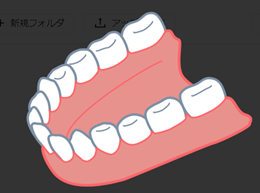
2. 咬み合わせの計画
咬合平面(こうごうへいめん)の決定について:
咬合平面とは、前歯から奥歯までの切端と先端どうしを結ぶとできる平面のことです。
患者さんの咬み合わせの高さや水平的な位置を考慮して、理想的な咬合平面を設定します。
これは美観だけでなく、機能面でも重要です。
もっとも上アゴの咬合平面は、ある程度の指標が使えます。
だから上の入れ歯の咬合平面が全然合わず使えない入れ歯になってしまうことは自分は少ないです。
しかし極端にアゴが小さいとか歯の大きさ、高さが小さいせいで咬み合わせが極端に低いとか、上の入れ歯で極端に難しい症例もあります。
咬合力のバランス:
前歯と奥歯のバランスを考えてカチカチと垂直に噛んだ時に均等に力がかかるように設計します。
また前後左右にアゴを動かして歯ぎしりの運動をした時に変な引っかかりがあって入れ歯が外れないように歯並びを作ることが必要です。
これにより、よく噛めるようになり顎関節への負担を軽減します。
入れ歯で噛めることによって食生活も向上し誤嚥性肺炎の予防にもなります。
3. 試作用入れ歯(ワックスアップ)
ワックスアップ:
最初の試作用の入れ歯はワックスで作製されます。
歯グキに当たるピンク色の部分(床)をワックスで作って、そこにプラスチック製人工歯を並べます。
この仮のワックス床を患者さんが実際に装着して咬み合わせやフィット感、発音、見た目の確認が行われます。
とくにその中でも上の入れ歯において、顔の正中と前歯の正中を合わせることは大切です。
模型でもある程度は
「ここが正中かな」
という指標はあります。
しかし実際の顔面とズレていることも多いです。
だからワックス床に仮の歯並びを作って患者さんの口の中に装着して確認する工程が必須です。
たとえば下の歯並びと合わせて顔に合わせたら、顔が曲がって見えるようになってしまった。
そんなことが起こります。
必ず患者さんの顔を見て、多くの場合に修正をします。
ワックス床の調整:
患者さんの口の中にワックス床を合わせて、咬み合わせの高さや幅、歯の配置などを調整します。
模型では良さそうだったけど口に合わせたら咬み合わせが高すぎて口を閉じられなかったとか、よくあります。
このような誤差は入れ歯が完成してから修正することは難しいです。
ワックス床のうちに修正しておきます。
またこの時点で難しいということは入れ歯が完成してからも難しいことが多いですので患者さんにも説明して心構えをしておいてもらいます。
意外とそのような配慮が大切だったりします。
このプロセスを一回だけでなく何度か繰り返すこともあります。
こうしてワックス床で大丈夫と確認したら歯科技工所に発注して入れ歯を完成させてもらいます。

4. 最終的な入れ歯の製作
素材を選択する:
患者さんのライフスタイルや予算に応じて、樹脂製、金属製、またはセラミック製などの素材が選ばれます。
保険治療だとプラスチック製の床、金属バネ(クラスプ)です。
近年はマグネット義歯も保険治療に収載されました。
しかしマグネット義歯は後からトラブルが多く当院では扱いません。
マグネット義歯は見るなり治療をお断りすることもありますのでご了承ください。
プラスチック製の床だと強度に不安をお持ちの方もいると思います。
保険治療でも中に補強の金属線や補強床を埋め込むことができます。
だから強度も十分保てます。
咬み合わせの最終調整:
完成した入れ歯を患者に装着し、再度咬み合わせと床の適合を確認します。
5. 使用後のフォローアップ
定期チェック:
入れ歯の使用開始後も、定期的なチェックが必要です。
咬み合わせの安定性や入れ歯のフィット感を確認して必要に応じて再調整を行います。
とくに食事すると痛い、というのは入れ歯の床の直径数ミリほどの出っ張りが歯グキを傷つけて潰瘍を作っていることが原因です。
その数ミリを削合することで治ります。
ガマンし過ぎず歯科医師に相談することをお勧めします。