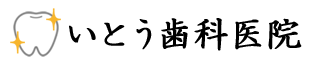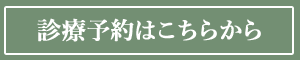杉並区西荻窪で入れ歯治療を数多く手がける
いとう歯科医院の伊藤高史です。
「あ、例の薬は飲んでから来ました」
と言って入ってこられたのは60代男性のKさん。
歯はそろっていて入れ歯もありません。
歯の揺れもありません。
数本の虫歯治療と定期的な歯周病治療を行なう治療計画を立てたのですが、定期的な歯周病治療を行なうために、解決しなければならない問題がありました。
定期的な歯周病治療とは
・超音波の力で歯石を除去する「スケーリング」
・回転するエンジンの力でブラシと特殊なペーストで歯面の汚れを除去する「機械的歯面清掃」
・9000ppmという高濃度のフッ素を歯に塗って虫歯を予防する治療「フッ化物歯面塗布処置」
を行ないます。
普通の場合には問題になることは何もない治療です。
しかしKさんの場合に問題となるのは「スケーリング」。
何も対策を講じなかったらスケーリングが絶対にできない事情がありました。
一般的には歯医者だけでなく歯科衛生士でもできる業務ですが、難しくしているその事情とは…
心臓の病気です。
具体的には心臓弁膜症でした。
・心臓弁膜症(しんぞうべんまくしょう)とは、心臓にある4つの弁のどこかに異常が起こり、弁の働きができなくなる病気です。
弁が固くなったり切れたり癒着したりすることで、血液の流れをコントロールできなくなり、心臓に負担がかかります。
放置すると心不全や突然死を引き起こす可能性があります。
弁膜症には「狭窄」と「閉鎖不全」の2つのタイプがあり、弁の開きが悪くなる「狭窄」と、弁が閉じなくなり血液が逆流する「閉鎖不全」があります。
また、両方が同時に起こることもあります。
とくに「大動脈弁」と「僧帽弁」の異常は頻度が高く、重要です。
高齢化の進行とともに加齢による弁の変性や石灰化が増えており、65歳以上の約10人に1人が罹患すると言われています。
参考文献:https://www.cvi.or.jp/9d/862/
心臓の病気と歯周病との関連が近ごろは注目されるようになりました。
スケーリングを行なうと歯グキから出血します。
歯グキに炎症を起こしている菌を取り除く意味もあるのですが、逆に出血するということは口の中のバイ菌が血管の中に入り込むということでもあります。
するととくに歯周病の原因菌が血管を通って体の中を巡り、心臓にくっついて病気を引き起こすことが分かってきました。
動脈硬化や感染性心内膜炎は命に関わる病気です。
・動脈硬化について

まずは動脈とは何か、そして動脈硬化とはどのような状態なのか、私たちの身体にどのような影響を及ぼすのかを簡単にみていきましょう。
動脈の役割
血管には大きくわけて動脈、静脈、細小動脈、毛細血管の4つがあります。
このうち動脈は、心臓から血液を全身に送り届け、酸素や栄養分を運搬する役割を担っています。
動脈は、内膜、中膜、外膜の3層からなるパイプのような構造で、心臓から送り出された血液は、約20秒で全身に届けられます。
心臓から勢いよく押し出される血液を滞りなく全身に届けるために、動脈は強く、柔軟性があります。
動脈の柔軟性を保つうえで重要な働きをしているのが、動脈の内膜の表面にある血管内皮細胞です。
血管内皮細胞は、血管が収縮したり拡張したりする機能を維持する物質を作り出しています。
動脈硬化とは?
動脈硬化とは、文字どおり動脈が硬くなる状態のことです。
この過程は加齢によるところもありますが、個人差が大きく、とくに血液中のコレステロールが強く影響しています。
なかでもLDL−コレステロール(悪玉コレステロール)が多く、HDL-コレステロール(善玉コレステロール)が少ないと動脈硬化が進みやすいことがわかっています。
動脈硬化になると、血管や心臓に大きな負担がかかって心臓の機能が低下したり、血管が破れて生命にもかかわる大きな病気を発症するリスクが高くなります。
動脈硬化には、粥状動脈硬化(アテローム性動脈硬化)、中膜硬化(メンケベルク型動脈硬化)、細動脈硬化がありますが、一般的に動脈硬化といえば、粥状動脈硬化のことを指します。
生活習慣病や肥満などにより、血液中のコレステロールが増加したり、高血圧や高血糖の状態が続くことで、血管壁に負担がかかります。この状態が長く続くと、血管内にLDL-コレステロールや細胞が蓄積していきます。
これを粥腫(じゅくしゅ)といいます。
粥腫が蓄積することで血管が狭くなったり、粥腫が剥がれたりすることで血液の流れを塞いでしまうことにもなります。
動脈硬化を起こした血管は、ちょうど古い水道管が汚れて詰まったり、さびが剥がれやすくなるのと同じと考えるとわかりやすいでしょう。
血管が狭くなると必要な酸素、栄養が全身に行き渡りにくくなり、さまざまな臓器や組織に影響が及びます。
さらに血管が詰まってしまうと、臓器や組織に血液が流れず、その場所が壊死して狭心症や心筋梗塞、脳梗塞などの心臓や血管の病気を発症しやすくなります。
また、硬くなった血管はもろく、破れやすいため、脳出血やクモ膜下出血の発症リスクが高まります。
参考文献:動脈硬化NET
https://www.domyaku.net/about/
・感染性心内膜炎とは
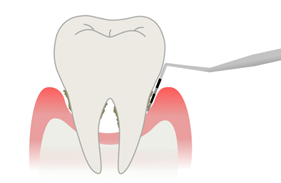
感染性心内膜炎(Infective endocarditis)は、心臓の内側に細菌が感染し、これによる心臓弁の穿孔等の炎症性破壊と菌血症を起こす疾患です。
起炎菌としては口腔内常在菌である緑色連鎖球菌や黄色ブドウ球菌が多く、弁尖などを破壊することによる心不全がもっとも危険です。
「そんな大げさな」
と思われるかもしれませんね。
歯科治療によって血管にバイ菌が入る「菌血症」の確率は、これまた数字で出ています。
「日常生活や歯科治療における菌血症の発生頻度」によると
抜歯で10~100%
スケーリングで8~79%
となっています。
こんな高い確率ならば予防が絶対に必要です。
参考文献:http://www.kankyokansen.org/journal/full/03405/034050237.pdf
それではどのように対応するか。
このような症例に対しては実は対応方法が決まっています。
入れ歯治療などは口の大きさ、入れ歯の形、適応できる範囲、個人の好みなど個人差があまりに大きいので、それこそ百人の歯医者がいたら対応方法が百通りある、みたいになってしまいがちです。
いっぽうこの心臓に病気を持つ患者さんの、感染性心内膜炎を予防する方法には概ねハッキリした一つの答えがあるのです。
「感染性心内膜炎の予防と治療に関するガイドライン」
です。
参考文献:https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/02/JCS2017_nakatani_h.pdf
保険治療で、入れ歯と口の機能検査ができます。隠れた不調がわかります

歯科で出血するような治療を行なう場合、予防的抗菌薬投与を行なうことが推奨されます。
具体的にはアモキシシリンという古典的ながら今でも歯科では第一に推奨される抗菌薬を2グラム。
スケーリングなどを行なう1時間前に単回投与。
と定められています。
歯科治療で使うアモキシシリンは1錠中に250ミリグラムなので8錠を一気に飲むことになります。
ちなみにこの8錠は、歯医者では処方できません。
私が処方できれば歯の治療前に病院へ行く煩わしさがなくて良いのですが、そうはいきません。
たとえば歯医者が処方せんに
「アモキシシリン8錠、単回投与」
などと書いて薬局に持っていったら、薬局から問い合わせが来てしまいます。
歯医者はそのような薬の処方が保険治療で認められていないからです。
なぜ歯医者が処方してはダメなのか?
なぜならその抗菌薬は感染性心内膜炎の予防のために使うわけですが、感染性心内膜炎を検査、診断し治療できるのは歯医者ではなく医師だからです。
歯医者は感染性心内膜炎の検査、診断、治療はできません。
だから感染性心内膜炎を予防するための抗菌薬8錠は医師に処方してもらう必要があるわけです。
では抗菌薬を処方してもらいたい場合に医師と歯医者との連絡をどうするか?
これもまた保険治療においてルールが決まっています。
それが「診療情報等連携共有」です。
歯医者から医師へ紹介状のような形で文書提供し医師から返事の文書を受け取ることで行なうものです。
当院ではもう決まったひな型があって、必要事項を記入して医療機関に郵送できるようになっています。
Kさんの場合も医療機関と連絡を取り合って、スケーリングの前には医療機関で抗菌薬を処方していただくことになりました。
余談ですが歯医者の求めに応じて医科が文書で対応してくださった場合には医科も保険点数が算定できます。
その項目などを示した案内文書も同封して医科の先生も対応しやすいように工夫というか配慮もしています。
論文をベースとしたガイドラインに則って保険治療の流れで行なうことなので安心して治療が受けられるように体制を整えています。
こうしてKさんは3~6か月ごとに安全に歯周病治療を行なって歯グキを良い状態に保っています。
また心臓の病気を予防することで医療自体にも歯医者が関わっているのです。