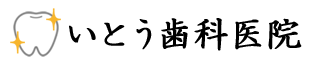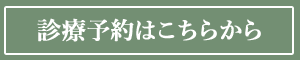「センセ、これはもう入れ歯を作り直すしかないですよね」
診察室に入って開口一番におっしゃるのは80代男性のMさん。
いやいや、口の中を見ないとわからないので。
Mさんが困っているのは歯の揺れ。
ひだり下の歯、3本が前後左右に大きく揺れます。
これは抜くしかない。
Mさんもこの歯は抜くしかないと理解されていました。
それで
歯を抜く→入れ歯を新しく作る
と考えたそうです。
Mさんは他院で作製された金属床の入れ歯を長年使っています。
入れ歯の出来具合は良好で、歯が揺れるまでは何ごともなく使っていました。
せっかく長年順調に使っている入れ歯なので新しく作り直すのはもったいない。
いえ、材料費とか通院回数とかがもったいない等とケチくさいことが言いたいわけではありません。
長年使い続けている入れ歯は、もう患者さんに馴染んでいます。
その長年の積み重ねを越える作品を新しく作るのは至難の業だと言いたいのです。
そんなに夢のように良い入れ歯がパパッと作れるわけではない。
仮にがんばって作ったとしても
「これまで使っていた物のほうがいいよ」
となって新しい入れ歯はケースに入ったまま…
そうなる可能性は高いです。
ではMさんのケースではどうするか?
ゆるい入れ歯には保険治療で歯科専用の入れ歯安定剤ティッシュコンディショナーを貼ると安定します

グラグラの歯、3本を抜いてから入れ歯にプラスチック製人工歯を継ぎ足す増歯修理を行ないます。
Mさんの場合、ひだり下の歯を3本抜くと残りはみぎ下に1本が残るだけになります。
もっとも今回の治療はみぎ下は関係ないので、入れ歯はそのまま使えます。
残っている歯に引っかける金属バネ(クラスプ)の修理などはしなくていいので簡単な修理です。
とはいえ歯を3本抜くのは意外と大きな治療ではあります。
抜いた穴(抜歯窩)から出血が多いので糸で縫い合わせて傷口をふさぐのと念のために化膿止めの抗菌薬を処方します。
抗菌薬とはいわゆる抗生物質のことです。
一般的な歯科で感染予防で使うのは、アレルギーがなければペニシリン系のアモキシシリンです。
参考文献:JAID/JSC 感染症治療ガイドライン 2016 ―歯性感染症―: 日本感染症学会
https://www.kansensho.or.jp/uploads/files/guidelines/guideline_JAID-JSC_2016_tooth-infection.pdf
アモキシシリンは一般的に「第1世代」と分類されます。
1972年に開発された古くからある薬です。
私の父もずっと使っていました。
第1世代とは、要するに「古い」ということです。
アモキシシリンはペニシリン系抗菌薬です。
似たものでセフェム系抗菌薬というものがあります。
セフェム系には第1世代~第4世代まであります。
ペニシリン系抗菌薬にはそのような世代はないので厳密には第1世代と言うのはおかしいのですが、ペニシリン系セフェム系と一緒くたに扱うことも多いのでペニシリン系抗菌薬のアモキシシリンも第1世代と通称されるようです。
もう30年くらいの話ですが当時最新だった第3世代経口セフェム薬がもてはやされた時代がありました。
商品名としてはフロモックス、メイアクト、セフゾン、トミロンなどです。
第2世代セフェム系抗菌薬のケフラールを大学病院でも使っていて、その後継薬が出たとのことで私も上司の先生の指示で処方した記憶があります。
しかし最近の研究でこの第3世代経口セフェム薬の薬効に疑義が呈されるようになりました。
経口の第三世代セフェム系抗生物質が「悪者扱い」される主な理由は、消化管からの吸収率が低く、効果が期待できない場合があること、そして耐性菌を生み出しやすいという点が挙げられます。
・吸収率の低さについて
経口の第三世代セフェム系抗生物質は、一般的に消化管からの吸収率が非常に低いとされています。
たとえばアモキシシリンは吸収率90%である一方、フロモックスやメイアクトなどは吸収率が20%程度しかないと指摘されています。
・効果が疑問視されるように
吸収されなかった薬剤は体外に排出されるため、腸管内の細菌感染以外にはほとんど効果がないと指摘されています。
・耐性菌の増加も
経口の第三世代セフェム系抗生物質は広範囲の細菌に効果を示すため、感染症を起こしている細菌だけでなく、腸内細菌などの常在菌も減少させてしまいます。
その結果、耐性菌が定着しやすくなる菌交代現象を引き起こす可能性を指摘されるようになっています。
・低カルニチン血症のリスク
ピボシキル基を持つ経口の第三世代セフェム系抗生物質は、重篤な低カルニチン血症を引き起こす可能性があり、低血糖や痙攣などの症状を引き起こすリスクがあることも指摘されています。
これらの理由から、経口の第三世代セフェム系抗生物質は、乱用や不適切な使用を避けるべきだと考えられています。
参考文献:学会トピック◎第34回日本環境感染学会総会・学術集会
「『だいたいウンコ』な経口第3世代セフェムは病院で採用すべきでない」のか?
「病院で第3世代経口セフェムの採用は必要か」Pros&Cons
2019/04/01
https://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/all/hotnews/int/201904/560401.html
定期的な入れ歯調整メンテナンス。費用は保険治療3割負担の方で総額約2,000~3,000円

このようなことから医科では処方することが少なくなっていますし、歯科ではもう第3世代経口セフェム薬を処方する理由は全くありません。
ただし2024年ころに薬の流通の混乱があって極度に抗菌薬が出回らなくなっています。
薬局でさえもアモキシシリンが入荷待ちなんてことがあって、そのような際は在庫がある第3世代経口セフェム薬をやむを得ず、仕方なく処方する場合があります。
ただそんな混乱があったものの2025年には少し回復しているようでアモキシシリン入荷待ちは減ってきています。
そのようなことで抜歯後に歯グキが腫れたり治りが悪くなったり全身に影響が出たりすることを防いでいます。
その日は他の患者さんが待っておられたので、その患者さん方の治療が終わるまでMさんには待合室でガーゼを傷口で噛んで圧迫する止血をしてもらいました。
45分ほど経ってから再び拝見するともう出血はなくなっています。
これならば入れ歯の増歯修理も簡単です。
やはり出血を気にしながらだと入れ歯修理も難しくなりますし、
患者さん→自分→他の患者さん
という感染もこわいので、しっかり止血。
そのために止血の時間を確保するのは大切なことです。
ところでその抜歯した部分へ、入れ歯にプラスチック製人工歯を継ぎ足すことでその日のうちに歯並びを回復させる増歯修理。
金属床入れ歯ならではの困難があります。
それは金属とプラスチックはくっつかない、ということ。
プラスチック製の入れ歯だったらプラスチックで修理するのは簡単です。
しかし金属の部分にプラスチックで修理するのはひと工夫必要です。
ひと工夫、それは金属床に穴を開けること。開けた穴にプラスチックを流しこんで物理的な嵌合力に期待します。
歯を削るエアタービンに金属を削る用のカーバイトバーを付けます。
たとえば金属のかぶせものを削ることはあるので、そういうバーはあるわけです。
とはいえ口の中のかぶせものよりは金属床入れ歯の方が格段に分厚いです。
だから削るのも大変。
穴を一つ開けるごとにカーバイトバーを一本使うので3本使って3つの穴を開けました。
これならば修理した部分は入れ歯にしっかり維持してくれます。
こうしてグラグラの歯、3本を抜いてから入れ歯にプラスチック製人工歯を継ぎ足す増歯修理は、その日のうちに完了できました。
「歯がある時よりも、これならしっかり噛めます」
Mさんは笑顔でおっしゃってくださいました。
ここに書いた内容を説明すると
「これは作り直したりせずに、このまま使った方がいいですね」
と考え直されたようでした。
修理が上手くできると、新しく作り直すよりもずっと短い時間で調子良い入れ歯に修理できます。
それは本当に患者さんのためになることです。
そんなMさんに聞かれたことがあります。
それは
「センセみたいに職人技を持っている歯医者って少ないでしょう?」
たとえば入れ歯を作るのも歯科技工所に丸投げ、歯列矯正も業者に丸投げ、そんな歯医者は増えていると思います。
でも今回のように職人技が活きる場面が入れ歯治療には数多く存在します。
昔に都心で勤務していた時代に
「もうこれからの時代はインプラントがあるから入れ歯なんか廃れてくるよ」
と先輩の歯医者から言われたことがあります。
…あれから30年近く経っていますが、そんな時代は来ていません。
【関連記事】→治療方針「以前に通っていた歯科医院でよく入れ歯のメンテナンスをしてもらっていたが、引っ越しや歯科医院の移転、閉院で通えなくなってしまい、どうしたらいいか困っている」