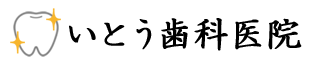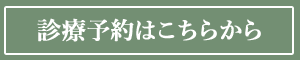t
「食事してると入れ歯が動いちゃって」
食べにくいし、食べたものが歯グキと入れ歯の間にはさまる。
普段は大丈夫だが食事すると歯グキが痛い
そんな訴えでいらしたのは60代男性のSさん。
上アゴの部分入れ歯は他院で作製されて、もう5年以上も使っているものです。
口の乾燥、口に限らない知覚の過敏がある難病のSさんには、入れ歯の違和感は耐えがたいものでした。
普通は前歯の後ろにピンク色のボディ(床)が付いていて上アゴ(口蓋)を覆っているはずなのですが、知覚が過敏で耐えられないため大幅の削られています。
前歯の後ろには申し訳程度に5ミリ幅くらいにピンク色の床が伸びているだけでした。
前の歯医者の先生も苦労されたのだと推測します。
とはいえ、その甲斐あってSさんは上の部分入れ歯を何とか使っていました。
ピンク色の床は大きく口蓋を覆うほうが入れ歯は安定します。
そりゃあたりまえ、というくらいのことです。
だから「部分入れ歯でも、総入れ歯のようになるべく床を大きくすべし」という主義主張の歯医者もいます。
それが間違っていると言うつもりは私もありません。
しかし患者さんによって条件は様々。
入れ歯治療で一番の大失敗…それは「患者さんが入れ歯を着けてくれないこと」。
大きくすべしの理論だけに偏った入れ歯を患者さんに押し付けても患者さんが「ヤダ」と言ったら論文としては正しくても治療は失敗、間違いなわけです。
ですから大学のセンセなどが見たら卒倒しそうな入れ歯なのですが、申し訳程度の床の入れ歯は正解と言えます。
しかし、やはり口蓋部分を削った代償がありました。
それは入れ歯が安定しないことです。
Sさんの入れ歯は左右4番目の歯に、それぞれ金属バネ(クラスプ)が付いていて入れ歯を口の中に維持しています。
クラスプが左右2つの入れ歯には、とくに欠点があります。
2つのクラスプを支点として入れ歯が回転運動をしてしまうことです。
テコの原理、簡単な物理の法則です。
・食事してると入れ歯が動く
・食べにくい
・食べたものが歯グキと入れ歯の間にはさまる
・普段は大丈夫だが食事すると入れ歯が強く当たって歯グキが痛い
こういった症状は入れ歯が動くと起こる典型的な症状です。
もっとも元から歯が左右に2本しかない、という患者さんは大勢おられます。
そんな患者さんにどう対応するかというと床を大きくして口蓋部分を広く覆う床によって回転を防ぐわけです。
ですからSさんの症状に対する策の一つは「床を大きくする」。
しかし先ほど述べた事情により床を大きくする策は取れません。
Sさんからもご提案がありましたし、そんな時に多くの歯医者が考える策があります。
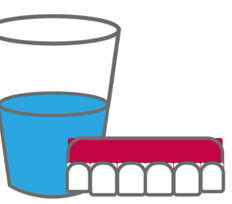
部分入れ歯の金属バネが折れても保険治療で修理できます
それは
「入れ歯を新しく作る」
こと。
もう古い入れ歯をリセットしてしまうわけです。
長年使っている入れ歯なので適合不良という理由で保険治療でも入れ歯を新しく作り直すことは可能ではあります。
しかし意外とそれは失敗します。
なぜならそこまで入れ歯を小さくしている方の特徴として多いのが
「歯が短い、咬み合わせが低い」
ことがあるからです。
Sさんの歯もすり減って短くなっていて高さが5ミリくらいしかありません。
入れ歯の高さもそのくらい。
そんな薄い小さい入れ歯を新しく作るのは通常の技工所では大変な困難を要します。
作製中の変形、誤差が1ミリでもあると、もう調整もできません。
また入れ歯を作る工程で入れ歯を石こうに埋めて重合して作って、その石こうを壊して取り出す。
そのような荒っぽい作業が必要なので、どうしても入れ歯には、ある程度の厚み、強度が必要になります。
あまりに薄く小さい入れ歯は作れないか、厚すぎる立派すぎる作品ができてくることになります。
多くの患者さんはもちろん歯医者ですら認識していない事が多いのですが、入れ歯を新しく作るのは意外にもリスキーです。
とくに難しい疾患を抱えているSさんには新しい入れ歯を「作らない」ことを強
くお勧めしました。
それではどうするか?
入れ歯の修理です。
Sさんは奥歯が左右に2本づつ残っていました。
左右とも4番目の歯にクラスプがかかっていますがその後ろ、5番目の歯は健全です。
この歯を利用しない手はない。
そこで今回はひだり上5番目の歯に新たにクラスプを増設する修理をご提案しました。
そうすればクラスプが2つ→3つとなります。
新たな3つ目のクラスプによって入れ歯の回転運動を防ぐ策です。
入れ歯を装着しておいて型をとって石こう模型を作ります。
模型上で新しいクラスプを作って入れ歯に埋めこみました。
もっとも増設することによって入れ歯が1センチほど長くなります。
その違和感に耐えられるかどうかは患者さん次第。
仮に耐えられなかったら、あきらめて削り取るしかないことをご説明してから修理に取りかかりました。
もっとも同じような修理を過去にたくさん手がけています。
クラスプ増設修理した入れ歯の成功率と入れ歯を新しく作った成功率の違い、は分かりません。
私が調べた限りでは、そのような論文は存在しませんでした。
…存在しないとは思います。
保険治療で入れ歯を修理を数多く手がける歯医者など、当院以外にはほとんどないと思われるからです。
論文にできるほどの症例数など集まらないでしょう。

入れ歯修理の費用は保険治療3割負担の方で総額約3,000~5,000円
大昔の祖父の時代、およそ100年前にははクラスプを作る方法がワイヤーを屈曲するワイヤークラスプしかありませんでした。
だから祖父はワイヤークラスプを自分で作っていました。
なぜ私がそんなことを知っているかというと理由があります。
私の父は祖父からワイヤークラスプの作り方を教わったと言っていたからです。
父の時代、1960年代くらいから遠心鋳造法の普及によってワイヤークラスプよりも精度が良いとの触れ込みで鋳造鉤が作られるようになりました。
鋳造は工程が多く複雑で作り手の精度も要求されるので歯医者はやらなくなりクラスプを作るのは歯科技工所の役割になってきます。
もっとも父が屈曲できるのはコツの要らない単純鉤まで。
私は歯科技工士に手とり足とり教わった成果として両翼鉤という複雑な形状のクラスプを作れるようになりました。
症例によっては両翼鉤じゃないとダメ、というケースは数多く存在します。
実際に保険治療のクラスプで多く使われるのは両翼鉤です。
だから歯医者が両翼鉤を屈曲できて初めて「どんな入れ歯でも90分で修理できる」と言い切れるわけですが、そんな歯医者は多くないと思います。
さすがに
「ワイヤークラスプなんかオワコン」
なんて言う歯医者はまだいませんが、そもそも使ったこともない歯医者は大勢いるでしょう。
ですから最近はそのような「手を動かせる歯医者」を増やすべくクラスプの曲げかたを動画で紹介したり歯医者向けの教育も手がけているところです。
まるで過去にタイムスリップしている気分ですが、今回の症例のように鋳造鉤や新しく作ることが上手くいかない話はたくさんあります。
むしろトラブルを抱えた入れ歯はこれから増えてくると思われます。
そんな時にワイヤークラスプを用いた入れ歯修理で解決できるのは患者さんにとっても助けになると確信しています。
それはさておき当院では、普段から使えている入れ歯ならば修理して多少大きくなったとしても、ほとんどのケースではそのまま不自由なく使えています。
知覚過敏の難病の症状がどのくらいかによりますが新しく作るよりは成功しそうです。
1時間で修理できた入れ歯を装着したSさん
「あっ、これなら全然大丈夫。違和感ないですよ!」
と笑顔で答えてくださいました。
新しい入れ歯を作ってしまったら、これほどスムーズに使えるようにはできなかったでしょう。
入れ歯修理の力を再認識した次第です。
今回行なったSさんのクラスプを作る修理した治療は、他の治療も含めて4回来院されました。費用は保険治療3割負担で総額約1万5千円でした(症状や治療部位によって費用は変わります)。
【関連記事】→入れ歯がゆるい「Q.上の入れ歯が落ちる、下の入れ歯が浮くなど、長年使用している入れ歯が最近外れやすくなって困っています。治療できますか?」